K-REACHとは?韓国の法律におけるPFAS規制の最新動向

投稿日:2025年11月4日

韓国の化学物質規制であるK-REACHは、EUのREACH規則(化学物質の登録、評価、認可および制限に関する規則)をモデルに導入された法律です。
近年ではPFASへの規制強化が国際的に進む流れを受けて、K-REACHでも一部のPFAS(有機フッ素化合物)が規制の対象となっています。
本記事では、K-REACHの概要や韓国のPFAS規制の最新動向について詳しく解説します。
INDEX
K-REACHとは

K-REACH(化学物質の登録及び評価等に関する法律)は、EUのREACH規則をモデルに韓国が独自に定めた法律です。EUのREACHと同様に化学物質の登録や報告などを義務付けるものですが、一部で韓国独自の特徴もあります。
K-REACHの目的
K-REACHは、韓国国民の健康と生活環境を守ることを目的に、韓国の化学物質の製造・輸入・流通を適切に管理するために制定された法律です。
一定量以上の既存・新規化学物質は事前登録が義務付けられ、危険性やリスク評価を通じて安全性が確認されます。
制定の背景には、2011年に発覚した加湿器殺菌剤(PHMG及びPGH)による健康被害事故があります。環境省の資料によれば、この事故により韓国国内で約120名の妊婦や幼児が死亡したと推定されています。この惨事を契機として有害化学物質管理法が改正され、2015年にK-REACHが新たに導入されました。
こうした事故の再発を防ぎ、持続可能な化学物質管理体制を確立する狙いがあります。
K-REACHの内容
K-REACHでは、韓国内で製造・輸入される化学物質を包括的に管理するため、既存物質と新規物質の登録が義務付けられています。
登録後は韓国環境部が有害性やリスクを評価し、必要に応じて使用制限や禁止措置を適用します。また、事業者には安全データシート(SDS、旧称MSDS)を通じて危険性情報を下流企業に伝達する責任があり、サプライチェーン全体での安全確保が求められています。
EUのREACH規則との違い
K-REACHはEUのREACH規則を参考に設計されていますが、いくつかの点で独自の仕組みを持っています。
韓国では有害化学物質について年次申告制度が導入されているほか、段階的登録の対象も「指定既存化学物質リスト(PECs)」に限定されるなど、独自の登録方式が採用されています。
一方、EUには「認可制度(Authorisation)」が存在し、特定有害物質の使用継続を認めるかどうかの審査が行われます。K-REACHにも許可物質に関する認可制度があり、特定有害物質の製造・輸入・使用前には環境部長官の許可が必要となる場合があります。
さらに、K-REACHは消費者製品中の重点管理物質について、製品単位での厳格な通知・評価を義務付けており、サプライチェーン全体でのリスク管理が徹底している点も特徴です。なお、殺生物剤についてはK-BPR(殺生物製品安全管理法)が別途適用され、K-REACHの適用除外となります。
K-REACHと関連する法律
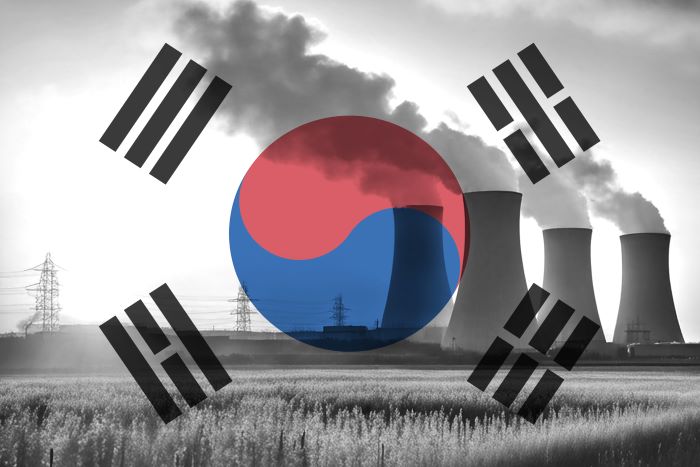
K-REACHは、化学物質管理法や産業安全保健法と同時に運用されることで、有害な化学物質から韓国国民の健康を守る仕組みになっています。ここでは、K-REACHと関連する2つの法律について詳しく解説します。
化学物質管理法
韓国では、1991年に制定された有害化学物質管理法を改正し、2015年1月にK-REACHと化学物質管理法が導入されました。
K-REACHが化学物質の登録・評価を通じて有害性やリスクを事前に把握する制度であるのに対し、化学物質管理法は化学事故の予防や緊急時対応、さらに製造業者だけでなく流通・販売段階まで含めた総合的な安全管理を規定しています。
また、本法は2012年に発生した大規模化学事故(亀尾市でのフッ化水素漏出事故など)を契機に強化された経緯があり、「重大化学事故の防止」を大きな柱としています。
環境への排出管理や廃棄物の適正処理についても規定しており、K-REACHと併せて韓国の化学物質管理体制を支えています。
産業安全保健法
韓国の産業安全保健法は、事業者に職場での化学物質曝露を防止する義務を課す法律です。
特に危険物や有害物質については、自律的な管理制度に基づき、事業者自身がリスク評価を行い、換気設備の整備や個人用防護具(PPE)の着用、安全教育の実施といった対策を講じることが求められます。
さらに、事業者は有害化学物質について安全データシート(SDS)の作成・提供やラベル表示を行う義務も負います。一定の有害化学物質は「管理対象物質」として指定されており、指定を受けた場合にはより厳格な管理措置が必要とされます。
この法律があることにより、労働者の健康保護と事故防止を両立させる仕組みが整備されており、K-REACHや化学物質管理法と合わせて包括的な安全網を形成しています。
K-REACHの規制対象物質

K-REACHでは、韓国既存化学物質リスト(KECL)に記載された物質について、年間1 t以上を製造または輸入する場合に登録が義務付けられています。
POPs条約(残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約)に基づき、PFOS、PFOA、PFHxSの3物質が規制対象となっており、韓国でも同様に規定されています。
また、PFOSとPFOAについては特定用途に限り、2026年6月2日までの時限的な免除が認められています(免除期限はPOPs条約の国際合意に基づく)。免除期間の終了後は、韓国国内において製造・輸入・使用が全面的に禁止されます。
| 物質名 | 特定免除 |
| PFOS(ペルフルオロオクタンスルホン酸) | 既設の消火泡(移動式・固定式)に限り、2026年6月2日まで使用可。 |
| PFOA(ペルフルオロオクタン酸) | 防液・防水性繊維、半導体(リソ・エッチング)、写真フィルム用感光コーティング、侵襲性/植込み型医療機器、既設消火泡などは2026年6月2日まで免除。 |
| PFHxS(ペルフルオロヘキサンスルホン酸) | 記載なし |
K-REACHの最新動向

韓国では2025年1月から、新規化学物質の登録閾値が従来の100 kg/年から1 t/年へと引き上げられ、規制対象範囲の合理化が進められます。
これにより、対象のPFAS(PFOA、PFOS、PFHxS)を年間1 t以上製造もしくは輸入する企業は、K-REACHに基づき登録が求められるようになります。
さらに同年8月からは、有毒物質を「人体急性有害性」「人体慢性有害性」「生態有害性」に区分する制度が告示され、リスク評価と管理の優先順位が一層明確化されます。
また、この区分とは別に、「有害性未確認物質(Hazardous Unidentified Substances)」については、正式な分類が確定するまでの間も予防的に有害物質として扱うことが求められています。そのため、企業には安全防護措置の実施が義務付けられる点に注意が必要です。
また、K Park 氏をはじめとする韓国の研究者チームが実施した疫学研究では、PFOAやPFHxSなど主要なPFASが国民の血清から高頻度で検出され、脂質異常症との有意な関連も報告されています。
こうした実態を踏まえ、今後はK-REACHにおける登録義務やPFAS関連の使用制限が一層拡大していく可能性があります。
K-REACHの最新情報を確認しましょう
韓国におけるPFAS規制の中心はK-REACHであり、その対象範囲や基準はEUのREACH規則とは一部異なります。しかし、国際的な規制強化の流れや国内の疫学研究の知見を踏まえれば、韓国の制度も今後さらなる見直しが進む可能性が高いと考えられます。
特にPFOA、PFOS、PFHxSといった物質は、環境・健康リスクが繰り返し指摘されており、規制が強まれば製造・輸入だけでなく、グローバルなサプライチェーン全体に影響を及ぼします。
企業にとってK-REACHの最新動向を把握することは、事業のリスクを回避して円滑に取引を維持するために欠かせない取り組みの一つといえるでしょう。
ユーロフィンのPFAS分析については
こちらからお問い合わせください
記事の監修者
 |
PFAS分析を行うユーロフィングループのネットワークを活かして、国内外の様々なPFASにまつわる情報を配信しています。 |
関連記事
 |
アジア諸国のPFAS規制の現状は?規制の傾向と最新動向について アジア各国におけるPFAS規制の最新動向を国別にわかりやすく整理。各国の法規制の違いや今後の規制強化の動きなどを解説。 |
 |
半導体製造におけるPFASの必要性は?規制動向や代替物質の開発について PFAS規制が進む中、半導体製造への影響や代替物質の最新動向を解説。今後の技術・法規制の変化に備えるための必読ガイド。 |
 |
PFASは中国でも厳格な規制へ。最新の法規制の流れと企業に必要な対応策 中国でもPFAS規制が強化中。重点管理リストやPOPs条約の最新動向を踏まえ、企業が取るべき対応策を解説。 |
【参考資料】
- 国際的な化学物質管理の状況について|経済産業省
- 韓国 化学物質登録・評価法|環境省
- 化学品の現地輸入規則および留意点|日本貿易振興機構
- 韓国 化学物質管理法|環境省
- 韓国 産業安全保健法|環境省
- 化学物質規制の国際動向|環境省
- Differences between K-REACH and EU REACH|ChemSafetyPro
- Levels of serum per- and polyfluoroalkyl substances and association with dyslipidemia in the Korean population」|K Park ほか(韓国の研究チーム)
- 残留性有機汚染物質の種類及び特定免除に関する規定|韓国環境部


