同じ検査でも結果が違う? NIPTの精度管理とスクリーニング検査のカットオフ値

同じ検査機器でも検査精度が変わる理由
「NIPTなどの出生前検査は、同じ検査機器や試薬を使っていれば、どこで受けても検査精度は同じ」と思いがちかもしれません。ところが実際には、検査における結果の信頼性は、検査室の精度管理体制によって変わることが分かっています。
ここでは、臨床検査室の品質管理や国際的な第三者認証(ISO 15189やCAP-LAP)がなぜ重要なのか、そしてそれがどのように結果の正確さにつながるのかを解説します。
臨床検査室の精度管理
同じ検査でも、精度管理・品質管理ができている検査室とそうでない検査室では、結果に差が出ることがあります。そのため、GeneTechではスタッフの教育や外部機関による認定など、さまざまな取り組みを通じて、精度を保つ努力をしています。
正確で信頼できる検査結果は、妊婦さんの安心にもつながります。そのため、精度管理体制はとても大切なことです。
ISO 15189やCAP-LAPなどの第三者認証とは?
臨床検査室を評価する、外部機関の主な認定について解説します。
 |
ISO 15189とは・臨床検査室の技術能力を証明する国際的な規格です。 |
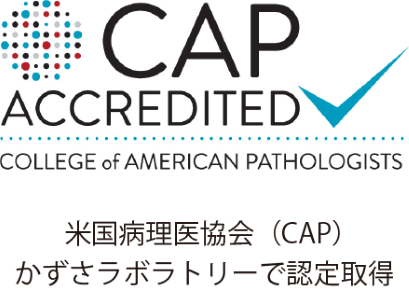 |
CAP-LAP(米国病理医協会の検査室認定プログラム)とは・認定取得にはPT(Proficiency testing、技能試験)の実施等が必要で、それにより、標準化を担保しています。 |
GeneTech株式会社の国内検査所(かずさラボラトリー)では、両方の認定を取得しています。そして、この2つの認定を国内で初めて取得したのは、GeneTechです。
認証を受けた臨床検査室の検査精度が信頼できる理由
CAP-LAPという制度は、病院や検査機関が正確な検査を行っているかどうかをチェックするための仕組みです。
その始まりは1946年、アメリカのペンシルバニア州。ある調査で、病院の検査結果に大きなばらつきがあることがわかりました。同じ検査でも病院によって結果が大きく違っていたのです。
この調査をきっかけに、1949年から「米国病理協会(College of American Pathologists、CAP)」が技能試験を定期的に行うようになりました。
今では、世界45か国・7,600以上の検査室がCAP-LAPの認定を受けており、検査の信頼性を守るための国際的な基準となっています。
特に、NIPTで使用する検査機器である次世代シークエンサーを用いた遺伝子検査業務の精度保証においては、CAP-LAPは高い実績があります。つまり、CAP-LAP認定の有無により結果の信頼性に差が出るといえるでしょう。
<関連リンク>
スクリーニング検査の「カットオフ値」とは?
NIPTは、妊婦さんの血液から赤ちゃんの染色体異常の可能性を調べるスクリーニング検査です。結果が「陽性」や「陰性」と判断される基準には、実は大切なしくみがあります。それがカットオフ値(閾値)と呼ばれるものです。
カットオフ値は検査の感度・特異度と直結し、さらに胎児ゲノム率によっても結果が変わることがあります。つまり、同じ検査方法でも、結果が違うことがあるのは、こうした背景があるからです。
ここでは、NIPTの結果に影響するしくみについて、ご紹介していきます。
検査精度(感度・特異度)とは?
感度と特異度の用語について、まずは説明します。
感度とは、対象の疾患である場合に検査で「陽性」と出る割合で、特異度とは、対象の疾患でない場合に、検査で「陰性」と出る割合のことです。
NIPTにおける感度・特異度のデータを下記に示します。
| 検出数 / 検査数 | 検出精度 | 95%信頼区間 | ||
| トリソミー | 正常核型 | |||
| ダウン症候群 (21トリソミー) |
270/271 | 6828/6845 | 感度:99.6% | 98.0-100.0% |
| 特異度:99.8% | 99.6-99.9% | |||
| 18トリソミー | 76/76 | 6634/6652 | 感度:>99.9% | 95.3-100.0% |
| 特異度:99.7% | 99.6-99.8% | |||
| 13トリソミー | 23/23 | 6581/6596 | 感度:>99.9% | 85.2-100.0% |
| 特異度:99.8% | 99.6-99.9% | |||
Eiben B,et al. Obstet Gynecol Rep;2021: Volume 5: 1-7
胎児ゲノム率が結果に与える影響
GeneTech NIPTで使用している機器メーカーの基準においては、胎児ゲノム率のカットオフ値は設定されていませんが、GeneTech NIPTではアメリカのステートメントに準じ、カットオフ値を単胎、双胎(双子)のそれぞれで設定しています。
これにより、胎児ゲノム率が足りないことによる偽陰性<注:本当は特定の疾患に対して「陽性」であるのに、「陰性」と判定される>の可能性を最少化することができます。
実際に、ドイツの13,607人の追跡調査では、胎児ゲノム率が3%<注:GeneTech NIPTのカットオフ値未満>で報告された陰性症例のうち1例で、21トリソミー(ダウン症候群)が偽陰性であったと報告がされています。
GeneTech NIPTの検査精度向上への工夫
スクリーニング検査では、検査精度(感度・特異度)は、分析精度とカットオフ値によって決まります。そのため、分析精度の品質管理を十分に行い、カットオフ値を工夫することで、より精度の高い検査を妊婦さんに提供することが可能です。
GeneTech では、今までの実績や経験を活かして、陽性・陰性の判定において、独自のカットオフ値を設定するなどの工夫により、偽陽性や偽陰性を減らす運用を実施しています。
たとえば、採血タイミングや測定誤差によって、機器メーカーが示す基準をまたいでしまう場合があります。
具体的には、1回目の検査では陰性であったのに、2回目検査では陽性と判定される場合です。GeneTech NIPTでは、機器メーカーの基準値の間に独自にグレーゾーンの値を導入し、無理に陽性・陰性を分類せず、判定保留として報告する運用をしています。
<関連リンク>







